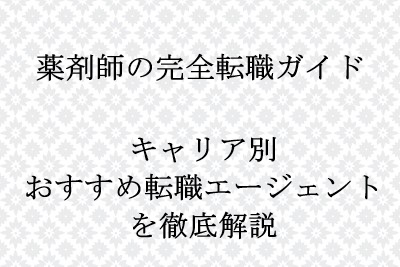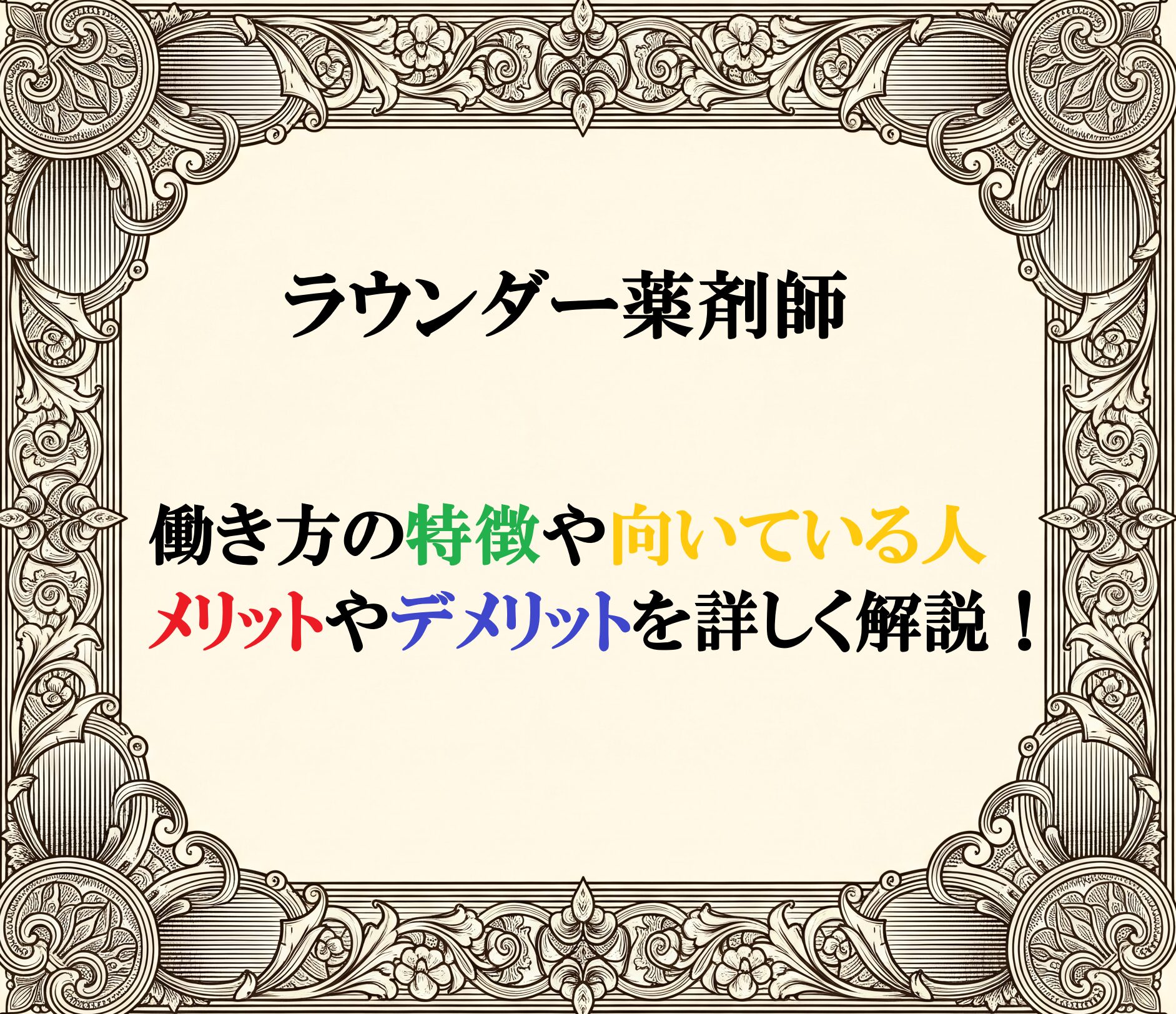「なぜ自分だけ、こんなにミスが多いんだろう…」
「患者さんや同僚とのコミュニケーションが、どうしてもうまくいかない」
「薬剤師の仕事は、もう限界かもしれない…」
もしあなたが今、このような悩みを抱え、「自分は薬剤師に向いていないのでは?」と苦しんでいるなら。
その原因は、あなたの「努力不足」や「能力が低い」からではないかもしれません。
それは、薬剤師という職業に求められる「能力」と、あなたの生まれ持った発達障害の「特性」との間に、ミスマッチが起きているのが原因の可能性があります。
この記事では、「発達障害の薬剤師が自分の特性をどのように仕事で活かすか」という問題を、「個人の能力」ではなく「環境と特性のミスマッチ」という視点から徹底的に解き明かします。
あなたが直面している困難の正体から、今すぐ実践できるセルフマネジメント術、そしてあなたの特性を「弱み」から「強み」に変えるキャリア戦略まで、具体的に解説します。
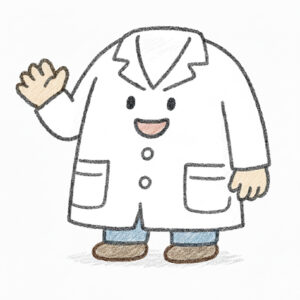
この記事を読み終える頃には、あなたが「自分らしい薬剤師」として輝ける道筋が、きっと見えているはずです!
なぜ薬剤師の仕事は「発達障害」の特性とミスマッチを起こしやすいのか

薬剤師の仕事は、他の職業にはない特有のプレッシャーがあり、発達障害の特性と衝突してしまうことが考えられます。
「正確性が求められる」ミスが許されない重圧
薬剤師の業務、特に調剤業務は、患者さんの命に直結します。
薬剤の取り違え、規格や投与量のミスは、重大な調剤事故につながりかねません。
この「絶対に間違えてはいけない」というプレッシャーは、発達障害の特性の一つであるADHD(注意欠陥・多動性障害)の「不注意」と、非常に相性が悪いのです。
「対人スキル」:薬だけでなく「心」も扱う難しさ
薬剤師の仕事は、単に薬を調剤して説明するだけではありません。
服薬指導では、患者さんの不安を察し、微妙なニュアンスを汲み取り、治療に前向きになってもらうための声掛けが求められます。
また、患者さんが薬の飲み方や注意点についてどの程度理解できているか、相手の反応を見ながら判断し、適切な指導をする必要があります。
この「暗黙の了解」や「相手の気持ちを察する」能力は、ASD(自閉スペラム症)の特性である「社会的コミュニケーションが困難」を持つ方にとって、極めて高いハードルとなります。
「発達障害グレーゾーン」の苦悩:自分を「ダメ」だと思ってしまう
深刻なのが、正式な診断を受けていない「グレーゾーン」の方々です。
この結果、「自分は努力してもできないダメな薬剤師だ」と自分を責め続けてしまうのです。
発達障害のある薬剤師が直面する「3つの壁」

あなたの感じる「つらさ」は、具体的にどういった業務で現れているでしょうか。
調剤業務:「不注意」と「過集中」が招くエラー
調剤業務は発達障害の特性を持つ人にとって多くのミスを誘発する要因が多数あります。
ADHD(不注意・多動性)
- 類似薬の取り違えや、規格の見間違い。
- 液剤や散剤の計量ミスが起きやすい。
- 落ち着かず、一つ一つの確認作業が疎かになりがち。
- じっとしてられず長時間の薬歴記入や報告書作成ができない
ASD(過集中・マルチタスク困難)
- 一つの作業に没頭しすぎ、電話や仕事の頼みなどの周囲の変化に気づけない。
- 患者さんからの急な質問や在庫不足など不測の事態に思考がフリーズし、臨機応変な対応が苦手。
服薬指導:コミュニケーションで「察する」難しさ
服薬指導の難しさは、「薬の使い方などを正しく説明すること」と「患者の不安に寄り添うこと」を良い塩梅で両立することにあります。
ASD特性を持つ方は、薬剤情報の説明は完璧にこなせても、患者さんの表情や声色から隠れた気持ちを察するのが苦手な場合があります。
その結果、相手の気持ちに配慮した対応ができず「冷たい」「機械みたい」と思われ、信頼関係が上手く築けないという事態に陥りがちです。
職場環境:「過敏な感覚」が集中力を奪う
薬局は、感覚的な刺激に満ちています。
例えば
- 自動分包機の稼働音
- 監査システムのビープ音(「ピー」とか「ピッ」という音)
- 複数の話し声や電話の音
- 蛍光灯の眩しさ
- 薬剤の匂い
ASDの方に見られる「感覚過敏」の特性を持つ方にとって、これらは単なる「不快感」ではなく「苦痛」を感じる場合があります。
常にこれらの刺激を意識してしまうため、業務をこなすのに多大な集中力を要し、すぐに疲労を感じてしまいます。その結果としてミスを誘発してしまうのです。
発達障害の人が人間関係で苦労すること

業務だけでなく、職場の人間関係も「見えざる障壁」となります。
「曖昧な指示」が分からない!
ASD特性を持つ方は、言葉を文字通りに受け取る傾向があります。
「これ、いい感じにお願い」「手が空いたらやっといて」といった曖昧な指示が理解できず、相手の意図と違う行動をとってしまいがちです。
相手の状況を考慮するのが苦手
医師への疑義照会は、薬剤師法で定められた重要な義務です。
しかし、ASDの「ルールへの強いこだわり」が、相手(医師や病院スタッフ)の状況を考慮せず、一方的に自分のやり方やルールを押し付けてしまい「融通の利かない対応」をしてしまうことがあります。
本人は職務に忠実であると考えているものの、周囲からは「融通が利かない人」と評価されてしまうのです。
疑義照会以外にも普段の業務で、すぐに共有した方がいいことを相手の忙しさや状況を考えずにまくしたてるように伝えてしまい、「相手のことを考えられない人」と思われてしまうケースもあります。
対策:SST(ソーシャルスキルトレーニング)で対人スキルを「学ぶ」
こういったことは、「人づきあいを基礎から学ぶ」SST(ソーシャルスキルトレーニング)で改善が期待できます。
これは仕事で使うプロフェッショナルスキルの習得を目的とした訓練です。
「ご不安でしたね」といった共感の定型句や、疑義照会時の「クッション言葉」などを「形式知(スクリプト)」として学び、実践で使えるスキルを身につけます。
「仕組み化」と「定型化」でミスを減らす!
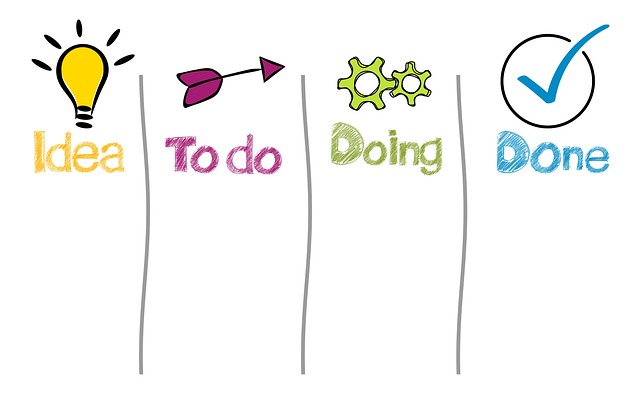
環境や他人は変えられなくても、自分の「やり方」「扱い方」は変えられます。
重要なのは、自分の「脳」に頼るのをやめ、「仕組み化」や「定型化」することです。
調剤ミスを防ぐ「仕組み化」:認知機能の外部化
タスク管理アプリの徹底活用
「今日やること」「発注リスト」などを記憶しようとすることをやめましょう。
やるべきことや気を付けることを紙に書きだしたり、アプリでToDoリストを作成して可視化しましょう。終わった仕事は線を引いたり消したりして、自分の仕事の現在地点を明確にしましょう。
「自分専用マニュアル」の作成
文字だらけのマニュアルではなく、写真やフローチャートを使用した視覚マニュアルを作ります。ハイリスク薬の棚に「赤いテープを貼る」など、視覚的な工夫も有効です。
周囲の許可を得る必要がある場合もありますが、覚えるのではなく「見て分かる」ようにしたらミスは大幅に減ります。
コミュニケーションを「定型化・視覚化」する
「かかりつけ薬剤師」を積極的にとる
不特定多数との会話が苦手なら、積極的に「かかりつけ薬剤師」になりましょう。患者さんとの関係を「浅い関係」から「長い付き合いで相手のことを良く知っている関係」に変えることで、コミュニケーションの難易度が劇的に下がります。
かかりつけ薬剤師と聞くとハードルが高いの様に思われるかもしれませんが、自分のことをたくさん話してくれる人やたくさん質問してくれる人は声掛けをすれば案外同意してくれますよ!

「指差し確認シート」など服薬指導ツールの作成
「副作用は?」と漠然と聞くのではなく、「①吐き気 ②眠気 ③便秘」と書かれた用紙で指差してもらうなど、コミュニケーションを「視覚化」し、聞き漏らしを防ぎます。
指さしシートは患者さんが口には出しにくい疾患について聞くときにも役に立ちます。
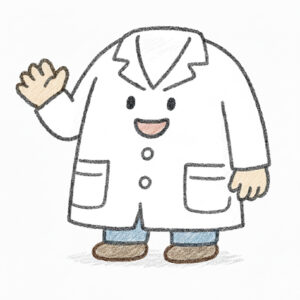
【特性を強みへ】発達障害の特性を活かす「働き方」「周りの配慮」

あなたの特性は環境次第で「強み」になります。
【事例】「なの花薬局」に学ぶ:業務分離で「正確性」を「強み」に
調剤薬局の「なの花薬局」では、「調剤アシスト」という職種を設け、発達障害のある方を積極的に採用しています。
その業務は、調剤ロボットがピッキングした薬の検品や商品補充など、対人コミュニケーションを最小限にし、「正確性」や「規則通りに淡々と進める」というASDの強みを最大限に活かすよう設計されています。
これは、薬剤師の業務を「対人業務」と「精密作業」に分担する、非常に優れた戦略です。

自分の得意なことに集中する働き方ですね!
こういった職場では自分の強みをいかんなく発揮できますね!
「周りの配慮」は特別扱いではない安全のために必要なこと。
今の職場で仕事の仕組み自体をを大きく変えることは難しくても「発達障害への配慮」を求めることは可能です。
ヒューマンエラーを防ぎ、患者安全を守るために必要なこととして提案しましょう。
例えば、「監査の精度を上げるため」に「静かな場所で監査業務を行うことを許可してもらう」(聴覚過敏対策)のは、医療安全の観点からも妥当なことです。
職場で相談できる「周りの配慮」具体例リスト
| 困りごと(特性) | 具体的配慮の例(環境) | 具体的配慮の例(業務) | 職場へのメリット(説得材料) |
| 聴覚過敏(雑音が集中を妨げる) | ・静かな場所での監査・投薬 ・パーテーションの設置 | ・ノイズキャンセリング耳栓の使用許可 ・電話応対をしない(特定の時間) | エラー率(ミス)の低下、業務精度向上 |
| 視覚過敏(蛍光灯が眩しい) | ・照明の照度調整、暖色灯の導入 ・席の配置変更 | ・PC画面の輝度調整 ・色付き眼鏡の使用許可 | 疲労軽減によるパフォーマンスの向上・維持 |
| 曖昧な指示の誤解(口頭指示がズレる) | ・チャット/メールでの指示のテキスト化 ・指示系統の一本化 | ・指示を「5W1H」で具体化するよう依頼 ・業務マニュアルの整備 | 業務内容の再確認の手間を省ける、指示の正確な伝達 |
| マルチタスクが困難 | ・集中ブースの設置 ・物理的に作業スペースを区切る | ・「集中タイム」を設定し、声かけを原則禁止する ・作業を細分化する | 調剤・監査スピードと精度の向上 |
| 口頭での聞き漏らし(申し送りを忘れる) | ・重要事項は必ずチェックリストや付箋で視覚化 ・ICレコーダーでの録音許可(確認用) | 申し送りミスによるインシデント防止 |
現職が限界なら…発達障害のある薬剤師のためのキャリア戦略

自分なりにできることをしても今の職場で働くことが困難な場合、働き方や環境の見直しが必要です。
「診断」と「障害者手帳」はキャリアのために必要なこと
「障害者というレッテルを貼られたくない」と診断を恐れる気持ちは分かります。
しかし、「診断をうけること」は、法的に自分を守り、支援を受けるために必要なことです。
障害者手帳を取得すれば、「障害者雇用枠」という選択肢が生まれます。
「クローズ就労」と「オープン就労」どっちを選ぶべき?
- クローズ就労(障害を隠す):一般枠で働くため、高い給与水準が期待できますが、周りの配慮は得にくく、ミスマッチによる疲弊のリスクが常に伴います。
- オープン就労(障害を開示する):障害者雇用枠で、障害への理解や合理的配慮を前提とした職場で働けます。データ上も、一般枠より職場定着率が格段に高いことが示されています。
長期的に同じ職場で働くことを考えた時、オープン就労は極めて合理的な選択肢となります。
活用すべき公的支援機関
まずは専門機関に相談し、自分の状況を客観視することから始めましょう。すべて無料で相談できます。
- 【STEP 1:総合相談】発達障害者支援センター:診断前でも家族だけでも相談可能。地域の支援拠点です。
- 【STEP 2:適職の評価】地域障害者職業センター:職業評価を通じて、自分の得意・不得意を客観的に分析してくれます。
- 【STEP 3:スキルの習得】就労移行支援事業所:就職・復職のための職業訓練や、職場探し、定着支援までを一貫してサポートします。
- 【STEP 4:復職支援】リワーク支援:休職中の方の職場復帰をサポートするプログラムです。
転職エージェントの賢い使い分け
【キャリアの分岐点】
公的支援と並行し、民間の転職エージェントを活用することで、より具体的なキャリアプランが見えてきます。ここで重要なのは「使い分け」です。
1. 障害者手帳がある(または取得予定)で「オープン就労」を目指す場合
障害者専門の転職エージェントを活用しましょう。
障害者専用の転職エージェント
- LITALICO仕事ナビ
- クローバーナビ
- ランスタッドチャレンジド
これらのエージェントは、障害者雇用の実績が豊富で、「合理的配慮」の種類から求人を検索できるなど、専門性が高いのが強みです。
2. 障害者手帳はない(or使わない)で「クローズ就労」を目指す場合
一般の薬剤師専門転職エージェントを活用します。
クローズ就労を選ぶ場合でも、エージェントに「マルチタスクが少ない職場」「調剤業務に集中できる環境」「教育体制が手厚いところ」といった形で、あなたの特性に合った「環境」を条件として伝えることが、次のミスマッチを防ぐ鍵となります。
オススメの転職エージェント
複数のエージェントに登録し、担当者との相性や求人の質を比較するのが、おすすめの方法です。
登録から相談、内定まで完全無料で利用できます。
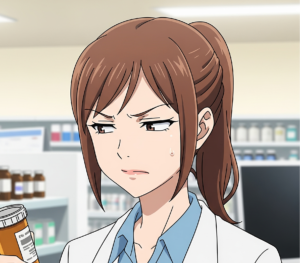
なんで無料で使えるの?
転職エージェントは紹介した人が内定・入社した時に企業から報酬をもらう仕組みなので、私たちは無料で利用できるのです!

まずは登録して情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。
(クリックすると公式サイトに移動します)
| エージェント | 主な特徴 | こんな人におすすめ |
| マイナビ薬剤師 | 利用者満足度◎!対面での手厚いサポートと豊富な非公開求人が魅力。 | 初めての転職で不安な方、じっくり相談しながら進めたい人。 |
| ファルマスタッフ | 大手調剤薬局グループが運営。調剤薬局の求人に強く、派遣のサポートも充実。 | 丁寧なサポートを受けたい人、高時給の派遣で働きたい人。 |
| レバウェル薬剤師 | 薬局や病院、企業など質の高い非公開求人が多い。 | 好条件の求人を探している人、キャリアアップを目指したい人。 |
| アイリード | 高年収や管理薬剤師など、好条件の非公開求人が多い | 今よりも年収を上げたい人、好条件な派遣薬剤師の求人を探している人。 |
| ファル・メイト | 高時給の派遣求人が豊富、派遣の福利厚生が充実 | 派遣社員として高時給で稼ぎたい人。 |
【まとめ】「自分らしい薬剤師」としてのキャリアを見つけよう
発達障害のある薬剤師が直面する困難さは、「努力不足」ではなく「特性と環境とのミスマッチ」によるものです。
目指すべきは、「苦手を克服して"普通"の薬剤師になる」ことではありません。
- 自分の特性(強み・弱み)を客観的に理解する。
- ツールや仕組み、支援機関を戦略的に活用し、無理に自分を変えようとしなくても成果が出せる環境に身を置くこと。
この2つへ考え方を変えることです。
あなたの「正確性へのこだわり」や「規則への忠実さ」は、環境次第で、他の誰にも真似できない「圧倒的な強み」となります。
まずは、一人で抱え込まず、公的支援機関や転職エージェントといった「プロ」に相談することから始めてみませんか。

その一歩が、あなたらしいキャリアを歩み始めるためのスタートとなりますよ!