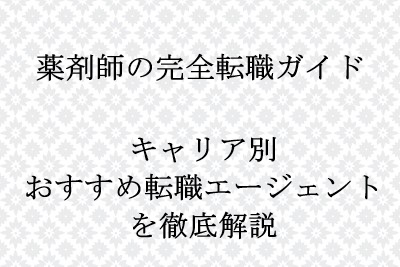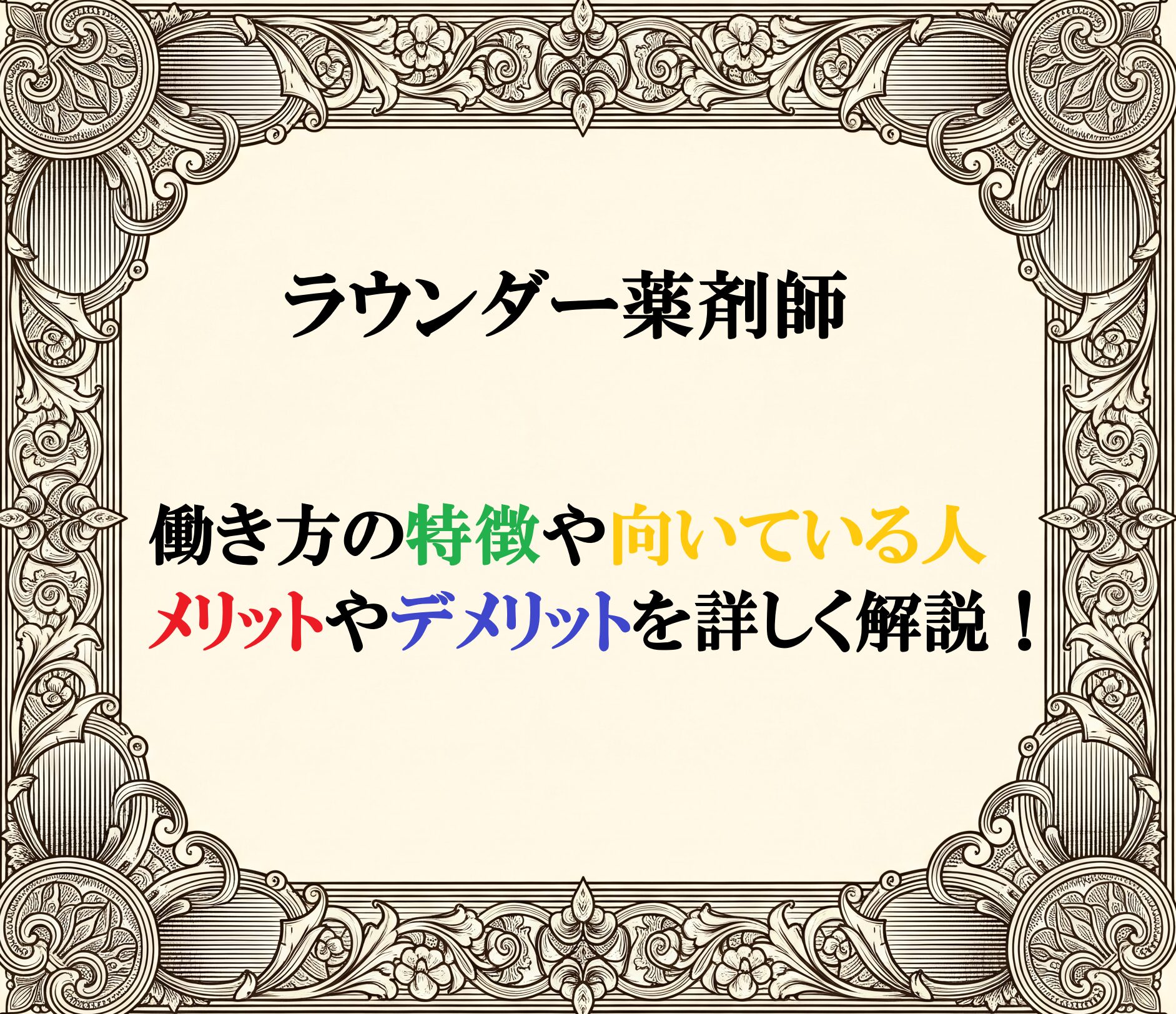薬剤師の皆さん、日々の業務、本当にお疲れさまです。
本記事では、「主体性」と「エゴ」の違いについて、筆者の薬剤師としての経験を交えて解説していきます。
日々の仕事の中で、「主体性って大事」と言われる一方で、時にそれが「自己中心的」「空回り」になってしまうことも…。そんな葛藤を感じたことはありませんか?
今回はそのような方に向けて、「正しい主体性」とは何かを考えるきっかけになれば幸いです。
主体性とエゴの意味・違いとは?
主体性(主体的であること)
「主体的に行動する」とは、自分の意志や判断に基づいて積極的に動き、その結果に責任を持つ姿勢を指します。
自分の意志を大切にしつつ、他者と協調する姿勢がポイントです。
エゴ
一方で「エゴ」とは、自分中心の考えや欲求を最優先する心のあり方。
一般的に「利己的」「自己中心的」といったネガティブな意味合いで使われます。
他者の気持ちや立場を考慮せず、自分の利益だけを追求する態度は「エゴが強い」と言われることもあります。
つまり
- 主体的=自分の意志で考え、責任を持って行動すること(協調性・成長志向)
- エゴ=自分本位・利己的な心のあり方(自己中心的・協調性に欠ける)
主体性は薬剤師の成長に欠かせない要素
筆者はこれまでの薬剤師としてのキャリアの中で、主体性こそが成長の鍵だと実感しています。
主体的に行動することで、さまざまな業務にチャレンジする機会が増えます。もちろん失敗も多くなりますが、その分、原因を分析し改善するチャンスが得られるのです。
例えば、
- 主体的に行動する
- 失敗する
- 原因を突き止め、改善策を考える
- 再度挑戦する
- 成功につながる
このような挑戦と改善のサイクルが自己成長を促してくれます。
また、主体的な行動をする薬剤師は職場でも評価されやすく、「頼りになる存在」として重宝されるでしょう。上司や同僚からの信頼も得られやすくなります。
【実体験】その主体性、相手は本当に求めている?
新人時代(1~2年目)
筆者も新人時代、「何事にも主体的に取り組むことが大切だ」と先輩に言われ、それを忠実に実行してきました。
当然ながら知識も経験も浅く、ミスを連発しながらも改善策を考え、前向きに仕事に向き合っていました。
この頃は「主体性=良いこと」と信じて疑いませんでした。
中堅時代(3年目~)
3年目以降になると、仕事にも慣れ、業務の幅も広がりました。かかりつけ薬剤師の獲得や加算の算定など、より難しい業務にも関わるように。
この時期、筆者はある気づきを得ます。それは――
「相手が求めていない主体性は、エゴになり得る」
具体例①:後輩へのアドバイス
かかりつけ薬剤師の声かけで断られ落ち込んでいた後輩に、良かれと思ってアドバイスをしましたが、反応は微妙…。
今思えば、求められていないのに指摘や助言をしたことで、相手の自己解決の機会を奪ってしまっていたのです。
具体例②:店舗応援での失敗
他店舗にヘルプに行った際、自分の店舗のルール(患者名+用法印字)で一包化を作成。しかし、ヘルプ先では「用法のみ」が基本。確認を怠った結果、分包紙と時間を無駄にすることになりました。
これらの経験から学んだのは、
「主体性は、相手のニーズに沿ってこそ意味がある」
ということです。
「正しい主体性」とは何か?
主体的に行動することは、薬剤師として成長するうえで非常に重要です。
しかし、その行動が自分本位であれば「エゴ」になってしまうことも忘れてはいけません。
ポイントは、「自分がどうしたいか」ではなく、「相手が何を求めているのか」を考えること。
正しい主体性とは、相手のニーズを察知し、それに応えるために自ら動くこと。
この姿勢が、周囲の信頼を得る薬剤師へとつながっていくのだと筆者は考えます。
まとめ|薬剤師として「エゴではない主体性」を発揮しよう
今回の内容をまとめると
- 主体性は薬剤師としての成長や信頼構築に必要不可欠
- ただし、自分本位な行動は「エゴ」になってしまう可能性がある
- 大切なのは「相手が求めていること」に目を向けて行動すること
皆さんが正しい主体性を発揮し、職場で信頼される薬剤師として活躍されることを願っています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。