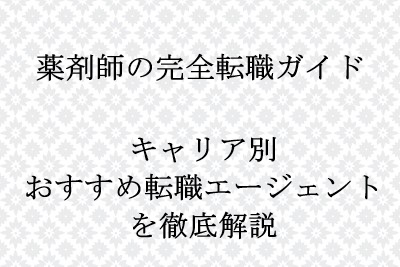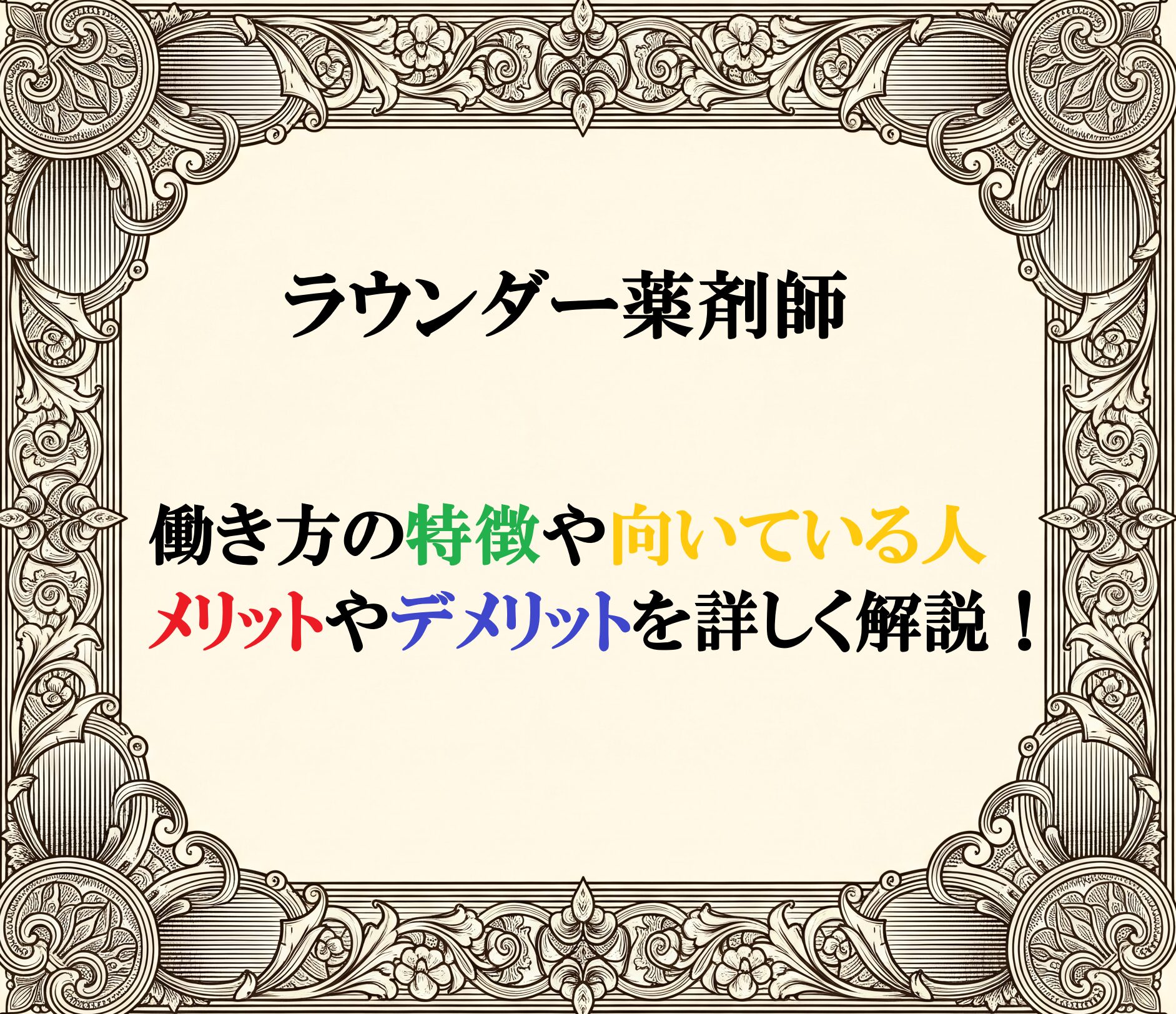はじめに:ギバーが組織を強くする!なぜ「与える人」が成功するのか?
薬剤師の皆さん、日々の業務お疲れ様です。
患者対応、調剤、在庫管理、地域連携と、多岐にわたる業務をこなす中で「もっと効率よく働きたい」「人間関係を円滑にしたい」「仕事で結果を出したい」と考えることはありませんか?
薬剤師の仕事は一見して個人の専門知識や能力が最重要に思えますが、実際は同じ職場の仲間、他職種との連携も大変重要です。
今回ご紹介する『GIVE & TAKE 「与える人」こそ成功する時代』は、そのヒントが満載の書籍です。
個人の利益ばかりを追求するのではなく、他者に貢献する「ギバー」こそが最終的に大きな成功を掴むという考え方が提唱されています。
一見すると、「与えるばかりでは損をするのでは?」と感じるかもしれません。しかし、この本を読み解くと、ギバーの「与える」行動が巡り巡って自分自身の利益や幸福に繋がるという、驚くべき真実が見えてきます。
薬剤師の皆さんが日々の業務でこの「ギバー」の考え方をどう活かせるのか、今回はギバーが組織にどのようなポジティブな影響を与えるのかという視点から解説していきます。
書籍紹介:『GIVE & TAKE 「与える人」こそ成功する時代』
そもそもギバーって?テイカー、マッチャーと言われる人との違いは?
人間関係における3つのタイプ
世の中には、人間関係における行動パターンで主に3つのタイプに分けられます。
- ギバー(与える人): 見返りを求めずに、他者に惜しみなく与える人。
- テイカー(奪う人): 自分の利益を最優先し、他者から奪おうとする人。
- マッチャー(バランスを取る人): ギブ&テイクのバランスを重視し、公平であることを求める人。
ギバーとは、自分のためではなく他者のために動ける人のことです。
他者に貢献することに喜びを感じ、自分の周りの人がより幸せに・成功に近づけるために行動します。
普段から他者貢献をしているため、多くの人から信頼され、よい人間関係や幸せな人生を歩むことができます。
ギバーの「協調性」がチーム全体の成果を最大化する
自分の利益より「全体の利益」を優先するギバーの働き方
薬剤師の仕事は自分自身の知識や考える力がとても重要ですが、決して一人で完結するものではありません。職場仲間や他職種といかにうまく連携できるかが仕事の出来を左右します。
この本で語られる「ギバー」の協力の仕方は、自分個人の利益よりも、グループにとって最善の利益になる行動をすることです。
例えば、
- 患者対応や疑義照会で時間をとられている同僚がいれば、自分の業務を一時中断して、ほかの患者さんの投薬や調剤をする。
- 在庫管理や発注業務を率先して取り組む。出荷調製品や経過措置の情報を集めて共有する。
- 薬歴が早く書き終わったら、もうすぐ来る患者さんの予製を作成する。
このような行動は、一見すると自分の負担を増やすように思えます。しかし、ギバーがこうした行動をとることで、チーム全体の生産性は格段に向上し、結果として自分自身も恩恵を受けることになります。
薬剤師の専門知識は個人の力に見えますが、その力を最大限に引き出すためには、周囲の協力が不可欠なのです。
「嫉妬」を「感謝」に変えるギバーの人間関係術
「優秀な人ほど、嫉妬されたり、疎まれたりする…」と感じたことはありませんか?
特に能力のある人は、その実力ゆえに周囲から攻撃の対象になることがあります。しかし、ギバーであれば、その心配は無用です。
ギバーは、その貢献的な姿勢によって、むしろグループに感謝される存在になります。同僚が嫌がる仕事を引き受けるので恨みを買うことなく、むしろ「ありがとう」と言われる関係を築けるのです。
これは、薬剤師の人間関係においても非常に重要です。例えば、
- 新しく導入された電子システムがあれば、その機能や操作方法を説明書類を読み込んだり、メーカーに問い合わせたりして同僚に伝える。
- 医師や他の薬剤師、ケアマネージャー等の地域医療スタッフから相談があれば、時間をとって誠実に対応する。
- 後輩の教育や同僚の相談に時間を惜しまず付き合う。自分の知識や経験を何でも教えるのではなく相手の能力の度合い(理解の度合い)に応じて、少しずつ相手の反応を見ながら教える。
失敗を恐れない!「心理的安全性」を築くギバーのリーダーシップ
「自分の責任」と「他者への称賛」が育む信頼関係
ギバーは、うまくいかないときは自分が責任を負い、うまくいっているときは、積極的に他の人を褒めます。これは、組織全体に「自分は貢献できている」と思えるような雰囲気を作り出す上で非常に重要です。
例えば、新しい業務フローを導入してうまくいかなかった際、「私の指示が悪かった」と率先して責任を負う。一方で、同僚や後輩の提案で効率化に成功した際には、「〇〇さんのおかげだね!」とメンバーを心から称賛する。
このような姿勢は、周囲に「何度失敗してもいい」という安心感を与えます。
これが「心理的安全性」です。
不利になったり、厳しく叱られたりする心配なく、新しい試みやリスクを冒せる環境は、業務改善や挑戦において不可欠です。
「視点のずれ」をなくすギバーの「共感力」
相手の立場に立って考えるギバーのコミュニケーション術
協力関係において、「テイカー」(与えるよりも多くを受け取ろうとする人)は、自分の観点からしか物事を見ず、他者が自分のアイデアや意見にどう反応しているかに気づかないことが多いです。
彼らは人それぞれの「視点のずれ」を考慮することがほとんどありません。
しかし、ギバーは違います。みんなに得をさせたいと思っているので、人の身になって考えます。
自分のものの見方にこだわるのではなく、他人の視点から見る能力は、協力関係で成功するギバーの得意技なのです。
これは薬剤師の業務において非常に役立ちます。
- 患者対応: 患者さんの話に耳を傾け、不安や不満を理解しようと努める。単に薬の説明をするだけでなく、患者さんの生活状況や価値観に合わせて、最も適した行動を考える。
- 食べ物との相性が悪い薬が処方されていれば、相性の悪い食べ物の一覧を用意してあげる。
アムロジピンやワルファリン等 - 1日複数回の服用が難しそうならば、疑義照会や情報提供をして1日1回の服用ですむ同種同効薬に変更する。
- 症状が治まっているにDO処方で出されている薬があれば疑義照会や情報提供をして処方を削除する
(場合によっては服薬調整支援料が算定できる)
- 食べ物との相性が悪い薬が処方されていれば、相性の悪い食べ物の一覧を用意してあげる。
- 多職種連携: 他の医療スタッフが何を求めているのか、どのような情報が必要なのかを彼らの視点から推測し、それに応じた情報提供や提案を行う。
- 医師等の医療従事者には患者さんが飲んでいる薬の薬学的な専門知識や投薬時の説明内容
- ケアマネジャー等の地域医療スタッフには患者さんのコンプライアンス、体調、生活状況
- 新人教育: 新人薬剤師が何につまずいているのか、新人自身の視点に立って考え、適切な指導方法を見つける。自分が新人だった時の頃を思い出してポイントを整理する。
この「視点のずれ」をなくす能力は、私たちがより良い医療を提供し、円滑な人間関係を築く上で、最も重要なスキルの一つと言えるでしょう。
まとめ:薬剤師として輝くための「ギバー」精神
『GIVE & TAKE 与える人こそ成功する時代』は、成功はチーム全体の協力や信頼関係があってこそ実現することを教えてくれます。
薬剤師としての業務においても、患者対応の質や在庫管理、スタッフ間の円滑なコミュニケーションは、まさに「全体の利益」を追求するギバーの姿勢によって強化されます。
まずは、自らの行動や考え方を見直し、どのように周囲に貢献できるかを考えることから始めてみてはいかがでしょうか。
さらに、この考え方は地域連携や他職種との協働にも応用ができ、将来的に薬剤師としての評価向上や各種加算の獲得にもプラスの効果が期待できます。
ギバー精神を実践することで、あなた自身の成長だけでなく、周囲の人々との信頼関係が深まり、薬局全体の成功へと繋がるはずです。
今回の内容で、何か新たな気づきはありましたでしょうか? 薬剤師の皆さんにとって、この記事が日々の業務や人間関係をより良くするきっかけになれば嬉しいです。
本ブログでは、「仕事のあり方」「人間関係」など薬剤師として働くうえで役立つ情報を発信しています。
気になる方は、ぜひお気に入りやブックマークをお願いします!