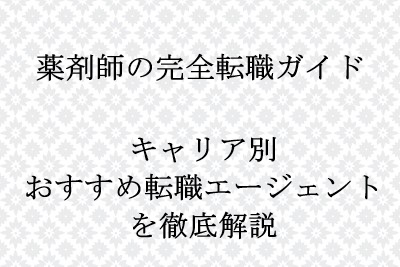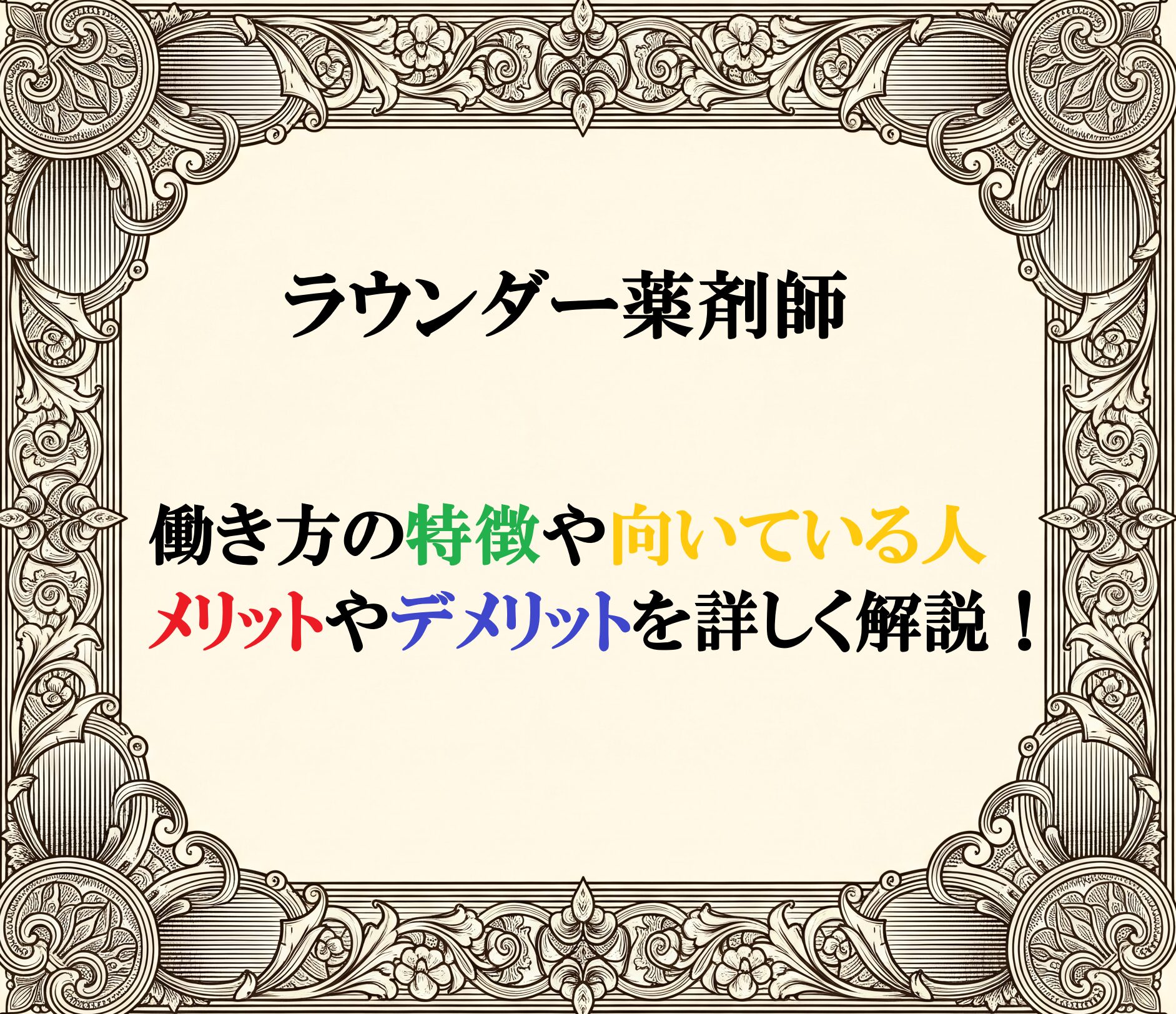はじめに:行動経済学は消費に関わる全ての人の役に立つ学問
薬剤師の皆さん、日々のお仕事お疲れ様です!
今回の記事は書籍「サクッとわかるビジネス教養 行動経済学」から薬剤師の仕事に応用できるエッセンスを抽出してお伝えします。
行動経済学と聞くと薬剤師とは関係ないと思われるかもしれませんが、実はそんなことはなく、日々の仕事に応用できるテクニックが満載なのでぜひ最後まで読んでいただけたらうれしいです!
そもそも行動経済学って何?
行動経済学=心理学+経済学
昔ながらの経済学では人は下の3つの考えに沿って行動すると考えられてきました。
- 超合理的:色々な選択肢の中から瞬時に最も効果の高いものを選ぶ
例)洗剤の1ml当たりの値段を計算して、一番安いものを買う - 超自制的:今と未来を天秤にかけて、未来に得られる利益が大きければ今はとことん我慢する
例)ダイエット中なので外食やお菓子はまったく食べない - 超利己的:自分の利益しか考えず、自分の行動によって他人が不幸になっても構わない
例)早くお店に入りたいので行列の一番前に割り込む
しかし、実際の人間はそのようなことはしません。
- 雰囲気で商品を選ぶ
- ダイエットしているのについつい食べ過ぎる
- 列があったら最後尾に並ぶ
このように昔ながらの経済学では説明できない特徴が人にはあるのです。
ここで出てきたのが心理学です。
つまり経済学に人間らしさ(心理学)をプラスしてできたのが行動経済学なのです!
マーケティング巨匠であるフィリップ・コトラーは「行動経済学はマーケティングの別称である」と語っています。
行動経済学はマーケティングで行われてきたことを学術的に紐解いたものです。
【仕事に活かせる】行動経済学のテクニック6選!
薬剤師の仕事に活かせる心理テクニックを書籍から6つの分類に分けてQ&A形式でお伝えします。
- 初頭効果、ピークエンド効果
- ハロー効果
- フレーミング効果
- 同調効果、バンドワゴン効果
- 互恵性
- イケア効果
Q:良い印象を残すために大切なことは
A:最初と最後が肝心
人の印象は第一印象に大きく影響されます。
これは、無意識に最初の印象が後に残り続けるからです。これを「初頭効果」と言います。
ほかにも、人がある事柄を思い出すときに働くのが「ピークエンドの法則」です。
これは、「ピーク(絶頂時)」と「エンド(最後)」が後から振り返った時に強く印象に残るという理論です。逆に、ピークとエンド以外は記憶に残りづらいともいわれています。
・薬剤師の仕事にどうに活かせるかのか
投薬時の初めのあいさつを丁寧にはっきり、最後には「お大事になさってください」と心を込めて言う。
これだけでも患者さんからは良い印象を受けることができます。
また、疑義照会をする必要があったり、薬などについて質問されることがあるでしょう。
これがピークになります。このときにいかに真摯で丁寧に対応するかで患者さんのあなたに対する印象は大きく変わります。
Q:「正確な評価」ができないワケとは?
A:「1つの評価」を「全体の評価」と考えてしまうから
身だしなみが整っている=仕事ができる
かわいい顔の人=性格がいい
笑顔が素敵=やさしくて信用できる
人や状況を判断するとき、ある面が優れていると他の面もすぐれていると思いがちです。
逆に、1つ残念なところがあると全体もネガティブに見えてしまうことがあります。
人は目立ちやすい特徴に引きずられて、他の特徴の正確な判断を怠ってしまいがちです。
この現象は「ハロー効果」と呼ばれます。
CMで人気のタレントが起用されるのもこのハロー効果を利用しています。
・薬剤師の仕事にどう活かせるか
普段の身だしなみと笑顔を心掛けることが大切です。
しわしわでインクがにじんだ白衣の薬剤師と、ピシッとしていて清潔な白衣を着ている薬剤師。
表情をまったく変えず坦々と説明をする不愛想な薬剤師と、笑顔で対応してくれる薬剤師。
どちらも後者の方が患者さんに良い印象を与えるのは明白です。
患者さんからすると、かかりつけ薬剤師になってもらったり、在宅医療の相談をするのは印象のよい薬剤師に方にお願いしたいはずです。
Q:表現方法を工夫するだけで人の行動は変えられるのか?
A:言い方1つで行動は大きく変えられる
例えば、経営難の企業の社長が、定例会で社員に経営状況を報告するとき。
「我々の会社は経営が厳しい、生き残れる可能性はわずかだ」と伝えると、「わずか」というネガティブなワードに引っ張られて聞いている社員の気分も落ち込みます。
しかし、「我々の会社の経営状況は厳しいが、皆で協力すれば生き残れる可能性は十分にある」と伝えたらどうでしょうか。
伝えている内容はほぼ同じなのに社員の感じ方は大きく変わることでしょう。
社員一人一人がこの会社をよくするために自分には何ができるか、この会社には何が足りないのかを主体的に考えるきっかけになるかもしれません。
このように、表現の仕方を変えると印象も変わることを「フレーミング効果」といいます。
・薬剤師の仕事にどう活かせるのか
患者さんの悩みに対してできるだけポジティブな声掛けをするようにしましょう。
例えば、疼痛があり生活に支障がでている患者さんを想定してみましょう。
患者さんが「痛みがあって家事や仕事がつらい、薬を飲んでいて以前よりはよいがなかなか治らない」と訴えてきたとき、
「前より良くなっているということはお薬がきちんと聞いているんですね。痛みと長く付き合っていく可能性はありますが、いつかよくなると信じて自分にできることをしましょう」
と伝えると今よりも良くなっている未来に目を向けて患者さんの気持ちも少しは晴れるのではないでしょうか。
Q:人は自分勝手に物事を決められない?
A:人は常に他人を意識する
人は意思決定をする際、周囲の意見を取り入れたり、自然と他の人をおもんばかったり、周りと比べています。決して、自分の意思のみで決めているとは言えないのです。
他の人と同じ行動を取ろうとすることを「同調効果」や「バンドワゴン効果」といいます。
「赤信号、みんなでわたれば怖くない」がいい例ですね。
逆に、他の人と違うことをしたくなる心の動きを「スノッブ効果」と呼びます。
白や黒の車が圧倒的に多い中で、たまに見かける赤やオレンジの車が一つの例ですね(単にその色が好きだという可能性ももちろんあります)
・薬剤師の仕事にどう活かせるか
患者さんにジェネリック医薬品を選んでもらったり、お薬手帳やマイナンバーカードをもって来てもらうとき等に有効な効果です。
例えば、ジェネリック医薬品を選んでもらう場合は、値段が安くなること、効き目・安全性が先発品と同等といった情報と一緒に「全国平均使用割合は80%以上」と付け加えると、みんながジェネリックを使っているのだったら自分もジェネリックにしよう・みんなが使っているなら危険なものではないだろうなと考え、ジェネリックの使用率が増えることでしょう。
お薬手帳とマイナンバーカードも同じ要領で、メリットだけをただ伝えるだけでなく、「持参率〇〇%!」「〇〇人に▢人が持参、利用進んでいます!」とみんなが使っていることを具体的な数字でアピールすると同調効果が働きやすくなります。
Q:なぜ他人に対して親切に接するのか
A:親切は自分にめぐってくると考えるから!
食事をごちそうしたり、お土産を買ってきたり、知り合いに対して親切な行いをするのは「互恵性」が働いているからです。
互恵性とは、自ら犠牲や手間(コスト)を払って、見返りを求める心理的性質のことで、自分が何かすることで相手からお返しがあることを想定しています。
また、似たように性質で「返報性」というものがあります。
これは、自分に何かしてくれた相手には、自分もお返しをしたいと思うことです。
見返りを求める「互恵性」と、お返しをしたいと思う「返報性」
2つの性質はうまくかみ合っていますね!!
・薬剤師の仕事にどう活かせるのか
かかりつけ薬剤師をとるときに返報性の考えが応用できます。
例えば、患者さんの悩みや困っていることの相談を聞き真摯に対応する。
処方箋で疑義があれば患者さんに了承を得て疑義照会する。疑義照会の結果は患者様にフィードバックする。
どちらも薬剤師としては当たり前のことをしただけですが、患者様は「自分のために一生懸命になってくれた」と感じます。
患者さんがこう考えているときは返報性が働いているので、かかりつけ薬剤師の提案もしやすく、説明からの了承がスムーズに進む傾向にあります。
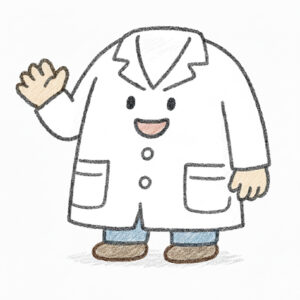
ただし注意点もあります。
疑義照会に時間がかかっている場合、患者さんの機嫌が悪くなっているときがあります。こういう時は提案をしても逆効果です…
相手の様子を見ながらイケる!となったタイミングを見極めましょう
Q:人はどんなものに価値を感じやすいの?
A:自分が苦労して手間暇かけたものに価値を感じやすい
自分で組み立てるタイプの家具やプラモデルがなぜ人気なのか、その理由は「自分で組み立てる」ことにあります。
つまり、苦労してつくるからです。
人は、自分で苦労して手を加えたものに対しては価格以上の価値と愛着を感じるからです。
これを「イケア効果」といいます。
一生懸命働いて稼いだお金は大事に貯金するのに、宝くじなどで棚からぼたもち的に手に入ったお金はパーッと浪費に使ってしまうのも同じ心理です。
・薬剤師の仕事にどう活かせる
1年目などの新人が活用しやすいテクニックです。
先輩の指導を聞く、しっかりメモをして実践する、ミスをしたら原因を突き止めて再度チャレンジする。
これを繰り返して後輩が成長すると先輩はうれしいものです。
イケア効果も働き、「もっとこの子を成長させてあげたい、いろいろ教えてあげたい」と考えます。
そうなると、自分では考えつかなかったやり方や手法をどんどん教えてくれるようになります。
新人が成長するには先輩の指導は欠かせません。分からないことを自分で考えるのも大事ですが、人に聞くのが一番手っ取り早いです。
イケア効果を使って、うまく人に頼って効率よく成長しましょう!
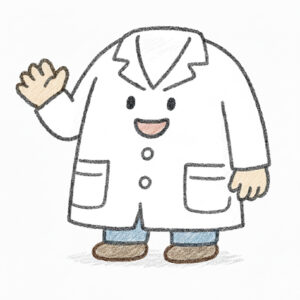
指導してもらって成長出来たら「仕事」で先輩方に報いましょう!
何かをしてもらったら、次は自分が相手に何をしてあげられるのかを考えるのが人間関係においてとても大事なことだと思います。
その他の心理テクニック
- デフォルト効果
選択の自由があるときに、あらかじめ選ばせたい選択肢を初期設定にすることをいいます。
例えば、WEBサイトなどの会員登録をする画面で「メルマガを受信する」に初めからチェックが入っているといったものです。
薬局で新患の方に書いてもらう初回質問票。
多くの薬局では先発品かジェネリックのどちらかにチェックをする形式をとっていると思われますが、これを「この薬局では国が推奨するジェネリックで調剤いたします。先発品をご希望の方は職員にお申し付けください」という形式に変えればデフォルト効果が働いてジェネリックを希望する方が増えると思われます。 - 極端の回避効果(松竹梅効果)
「激辛」「ふつう」「激甘」の3種類のカレーがあった場合、多くの人が「ふつう」を選びます。選ぶものが2拓だと人は迷いがちですが、3拓になると真ん中の選択肢が選ばれやすくなります。
このように人には極端な選択をさける傾向があります。
筆者が以前行ったドラッグストアでは3種類の血圧計が置かれていて、それぞれ値段が6000円、8000円、10000円でした。
8000円の血圧計には、オススメとポップが書いてあり、ドラッグストアとしては8000円のものを売りたかったのだと思います。
極端の回避効果をうまく使った良いマーケティングですね!
まとめ
今回は、書籍「サクッとわかるビジネス教養 行動経済学」から薬剤師業務に役に立つ心理テクニックを紹介しました。
内容を簡単にまとめると
- 初頭効果、ピークエンド効果:人の印象は最初と最後、最も盛り上がった時の影響を大きく受ける
- ハロー効果:一部分が良いと、その他も全部よく見える
- フレーミング効果:伝え方を変えるだけで、人の受け取る印象は大きく変わる
- 同調効果、バンドワゴン効果:人は他の人の行動に影響を受ける
- 互恵性、返報性:人が他人に親切にするのは見返りを求めるから。他人に何かをされると自分もその人になにかお返しをしたくなる。
- イケア効果:自分が手間暇かけたものにはより愛着がわく
本書では他にも実生活で役に立つ行動経済学の心理テクニックがイラスト付きで分かりやすく紹介されていました。
興味がありましたら、ぜひ手に取ってください!
おまけ
こんばんは、シマです。
今回の記事はいかかでしたか?
普段気づかないだけで人の心を動かすテクニックは日常の中にあふれているんですね。
敵にするとかなり厄介ですが、味方にするととても有用なものばかりでしたね。
行動経済学の本は初めて読んだので新たな発見がたくさんあって読んでてとても面白かったです!
アマゾンを見ると行動経済学系の本がたくさんあったので今後も記事にできたらいいなと思いました。
それでは皆さん、また会いましょう!